【授業レポート】未来を創造する「問い」を育てる──創造性開発演習・最終発表会
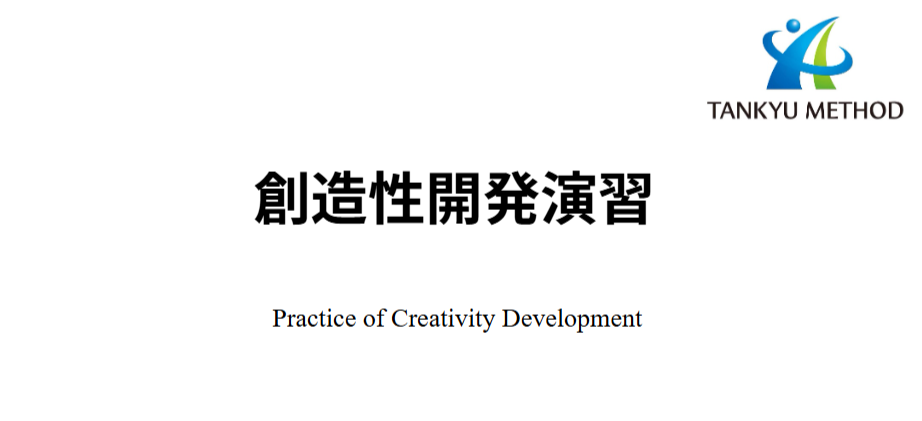
神戸情報大学院大学(KIC)で開講されている実践型授業「創造性開発演習」。その集大成となる最終発表会が2025年9月に実施され、ICTプロフェッショナルコースの学生たちが各チームで社会課題に挑んだ成果を発表しました。
社会の「今」と向き合い、未来を構想する演習
この授業では、AIやテクノロジーの進展、人口動態の変化、多様化する学びのあり方など、現代社会の複雑なテーマに対して、グループワークと問いの技術を駆使してアプローチします。
今年度の発表では、4つのチームがそれぞれ独自の課題設定と斬新な提案を披露しました。
都市と地方の格差に挑む「国家OS」構想チーム
「都市と地方の格差は、もはや“システム”の問題だ」──そんな視点から、国家機能のクラウド化やAI・ロボットによる地方インフラ再設計、「どこでもドア構想(勤務地と居住地を切り離す税制度)」など、大胆かつ構造的な提案を展開。
RESETフレームワークと生成AIを活用し、制度・技術・価値観のレベルから“格差が自動で是正される社会”の実現可能性を探りました。
不登校生に“選べる学び”を──AI時代の教育変革チーム
一律の教育スタイルが合わない子どもたちの現実を見つめ、AIとVR/ARを組み合わせた「個別最適な学び」のプラットフォームを構築。
感情データまで活用した学習プランの自動生成、バーチャル教室での臨場感ある体験、孤立を防ぐオンラインコミュニティなど、「不登校」の先にある未来の教育像を描き出しました。
スマホ依存×留学生=デジタル疲労の悪循環を断ち切るウェルビーイングチーム
孤独や文化適応のストレスからスマホ依存が進む留学生に焦点を当てたこのチームは、「禁止」ではなく「楽しい挑戦」で依存を改善するプログラムを提案。
1日3時間の“スマホ非使用チャレンジ”を軸に、文化体験、交流会、自然アクティビティなどの代替行動を設計。履歴書に書ける認定や地域連携インセンティブも用意し、デジタルウェルビーイングを楽しみながら実現する仕組みが注目を集めました。
社会人の「学び直し」を再設計する“社会人学校”チーム
リスキリングという言葉が広がる一方で、「何を学ぶべきか」「どう学ぶか」に悩む社会人は多い。
その声に応え、企業出資型の“社会人学校”という新たな教育モデルを提案。
就業時間内で学べる制度設計、実務家教員によるPBL(プロジェクト型学習)、成果を可視化するポートフォリオ制度など、学びが“自己投資”で終わらない設計が高く評価されました。
創造性とは、社会と向き合う力
創造性開発演習の根幹にあるのは、「問い」を立てる力です。正解のない課題に対し、観察し、問い、探究し、社会に提案する。このプロセスを経ることで、学生たちは自らのアイデアで未来を形づくる視点とスキルを身につけていきます。
KICでは、こうした実践を通じて、「テクノロジー × 社会課題 × 創造力」の交差点で活躍できる人材を育成しています。
あなたの問いが、未来を変える。
創造性開発演習は、ただアイデアを出すだけの授業ではありません。社会の本質に迫り、自分たちの手で答えを探しに行く場です。ここには、ただの“勉強”では得られない学びがあります。
▶︎ [創造性開発演習について詳しくはこちら]

