【KickBrain新記事更新】過去から未来を学ぶために。シンポジウム「震災における情報ネットワークの役割」~次世代のITエンジニアに送るメッセージ~
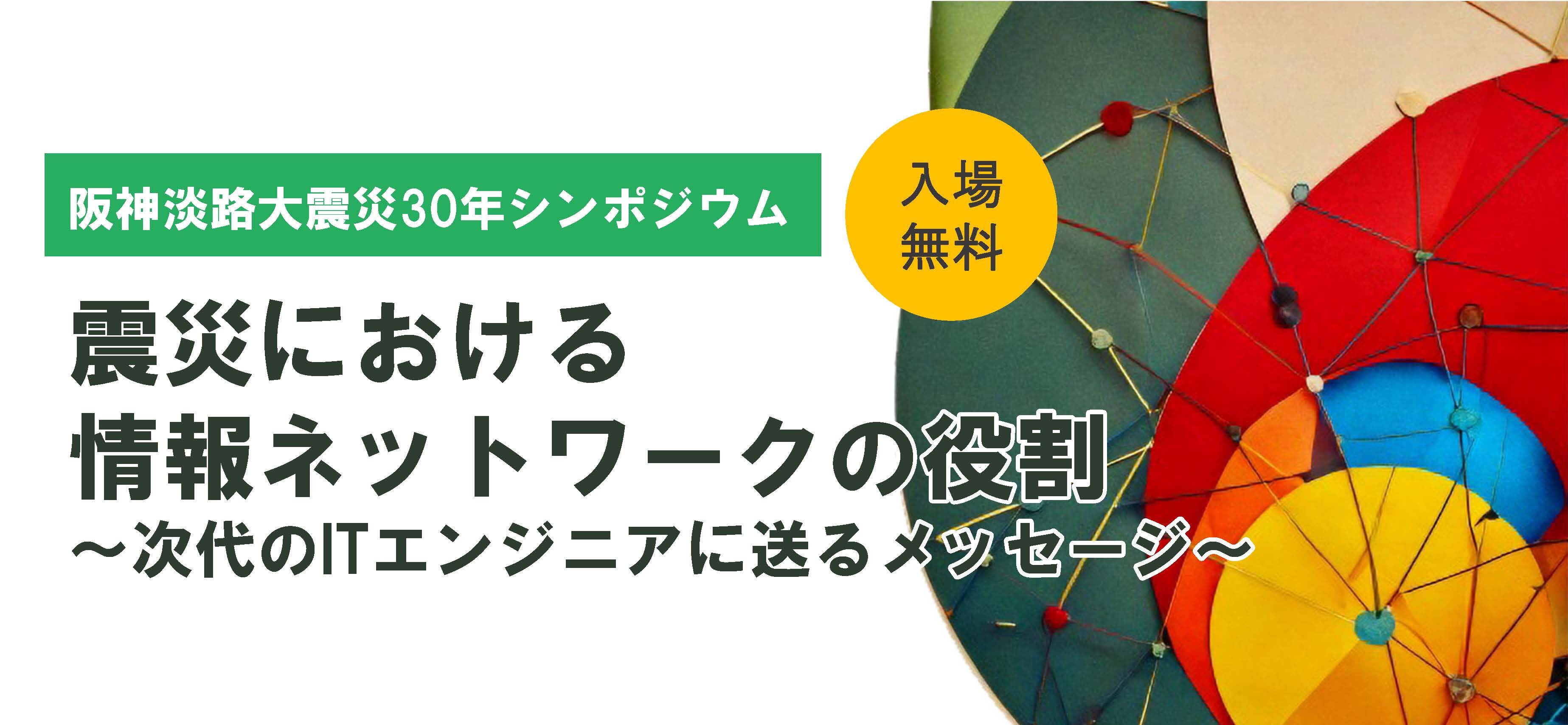
1995年1月17日、死者6,434名、負傷者4万3,792名、全半壊棟数約24万9,000棟※という、戦後最悪の未曾有の被害をもたらした阪神・淡路大震災。当時の日本は携帯電話もパソコンもわずかしか普及しておらず、インターネットにおいてはほとんど活用されていない時代。状況が見えず混乱を極めていく被災地で、「なんとかしなければ」と自らが持てる知識と技術を持ち寄り、さまざまな情報発信活を始めたエンジニアたちがいた。
彼らの活動はやがて「情報ボランティア」という新たなムーブメントを生み出し、今に続く防災情報システムの礎を構築。その後、2011年3月11日に発生した東日本大震災で、被災地の復旧・復興を支えた「シビックテック」という大きな流れへとつながっていった。
そして、阪神淡路大震災から30年を迎えた2025年。この大きな節目で、学校法人コンピュータ総合学園神戸電子専門学校、神戸情報大学院大学、神戸国際大学が主催し、兵庫県、神戸市、公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構が後援として開催されたシンポジウム「震災における情報ネットワークの役割」では、1995年2月4日に神戸市役所に集まり、ボランティアネットワークを立ち上げたメンバーが登壇した。地震発生後、アナログのビデオカメラで被災地を撮影し、日本で初めて世界へと発信した松崎太亮氏(神戸国際大学副学長)と芝勝徳氏(神戸外国語大学名誉教授)、メンバー集結の発起人となった山本裕計氏、パソコン通信を駆使しながら情報発信やデータベース作成に奔走した福岡賢二氏(神戸情報大学院大学学長代理)と小畑雅英氏(神戸電子専門学校非常勤講師)、神戸での経験を活かし22024年には能登半島地震の支援に赴いた行司高博氏(公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構研究戦略センター研究調査部長・防災DX官民共創協議会自治体部会長)の6名が学校法人コンピュータ総合学園・神戸情報大学院大学/神戸電子専門学校の北野館に集結し、それぞれの当時の活動や被災地復興にかけた想いを発表。モデレーターを勤めた大月一弘氏(神戸大学名誉教授)とともに、今なお大きな災害が続く日本の未来に向けて、「何を考え、何をしなければいけないのか」を語り合った。
※総務省 消防庁 阪神・淡路大震災について(確定報)参照

